『作曲』と聞くと、難しくてできないと思われる方が多いと思います。
実際、私の知り合いの音楽好き、歌好きの方々でも、
『作詞はできるけど、作曲はできないから誰かやってくれる人いないかなあ』
と言っている方が非常に多いです。
しかしながら、
作曲自体はそんなに難しくなく、誰でもできます。(断言!!)
ただ、取っ掛かりをどうすれば良いかがわからないということではないでしょうか。
作曲のやり方には正解はありません。
100人いれば100通りのやり方があるモノだと思います。
言い方を変えれば、その人にはその人に合ったやり方があるとも言えるかと思います。
とは言え、やり始めてみないと、自分にあったやり方を見つけ出すことすらできないですよね。
そこで、そういった方々がどう曲を創り始めれば良いかを、私自身の経験をベースにお話しできればと思います。
初めての作曲にトライしたいと考えている方の参考になれば幸いです。
スリーコードを覚えよう
作曲の取っ掛かりとしては、まずスリーコードを覚えることをおススメします。
極端な話をすれば、どんな曲もスリーコードで弾くことができます。
裏を返せば、スリーコードさえ弾けるようになれば、どのような曲も創れるようになるということだと理解していただければ良いと思います。
私も初めて曲を創ったのはスリーコードの曲でした。
そして、簡単なものでも自身のオリジナル曲が創れることがわかると、今度は違う感じの曲も創りたくなり、そのためにもっといろいろなコードを使う必要が出て来て、コード進行や音楽理論をイロイロと勉強し、現在に至っております。
スリーコードとは?
スリーコードとは、その調のベースになるコードであるKeyのコード、Keyコードから4番目、Keyコードから5番目の三つのコードのことで、音楽用語で言えば、ダイアトニックコードにおけるI、Ⅳ、Vのコードとなります。
(ダイアトニックコードについては、スケールとダイアトニックコードの回参照)
例えば、
KeyがC(ハ長調)なら、C、F、G
KeyがG(ト長調)なら、G、C、D
KeyがAm(イ短調)なら、Am、Dm、Em
が、そのKeyにおけるスリーコードになります。
ちなみに、コードを弾きながら歌うだけでも、弾き語りは成立しますし、アレンジを行う時もコードをベースに組み立てて行きますので、作曲する時にはメロディラインだけでなく、コードも指定して置く必要があります。
スリーコードを用いれば、どんなメロディラインでも創れる理由
『スリーコードを用いれば、どんなメロディラインでも創れる』と述べましたが、その理由を解説します。
まず、メロディラインには12音階すべての音が使えるわけではなく、key(調)によって使える音が決まっています。そして、その使用できる音を低音側から順に並べたものをスケール(音階)と言います。
例えば
key=C(ハ長調)のスケールは、ドレミファソラシド(C,D,E,F,G,A,B)
Key=G(ト長調)のスケールは、ソラシドレミファ#(G,A,B,C,D,E,F#)
そのKeyの楽曲のメロディには、このスケール上の音以外は、基本的に使いません。
正確に言うと、スケール外の音も使うことができるのですが、その使い方には、また細かいルールがあって、今のトコロそれは脇に置いておいて良いと思います。
(スケール外の音の使い方については、コードとメロディの関係の回参照)
そして、メロディと同じ音を持つコードなら、そのメロディに合わせて歌うことが可能になります。
これらより、『スリーコードを用いれば、どんなメロディラインでも創れる』理由は、
からです。
具体的に見てみましょう。
例えば、key=C(ハ長調)の場合
スケール⇒ドレミファソラシド(C,D,E,F,G,A,B)
スリーコード⇒C,F,G
各コードの構成音
Cコード⇒ドミソ(C,E,G)
Fコード⇒ファラド(F,A,C)
Gコード⇒ソシレ(G,B,D)
いかがでしょうか?
スケール上の音がすべてコード構成音に含まれていますよね。
なお、この法則は、Key(調)が変わっても当てはまります。
なぜなら、スケールとコードの構成音の関係は、こうなるように決められているからです。(スケールとダイアトニックコードの回参照)
スリーコード作曲にトライ
というわけで、スリーコードを適当に組み合わせて、鼻歌を歌ってみてくださいませ。
いかがでしょうか?
それなりに曲っぽくなっているのではないかと思います。
あとは、コードの順番を変えながら歌って、自分の心地よいメロディラインを探しつつ、歌メロとコードをレコーダーなどで記録して置けば、それでオリジナル曲を作曲したことになります。
これをキッカケに、作曲の楽しさを知り、作曲活動にハマっていただけると幸いです。
それでは本日はこれにて。
最後までご覧いただきありがとうございました。
それでは、また。
MASA
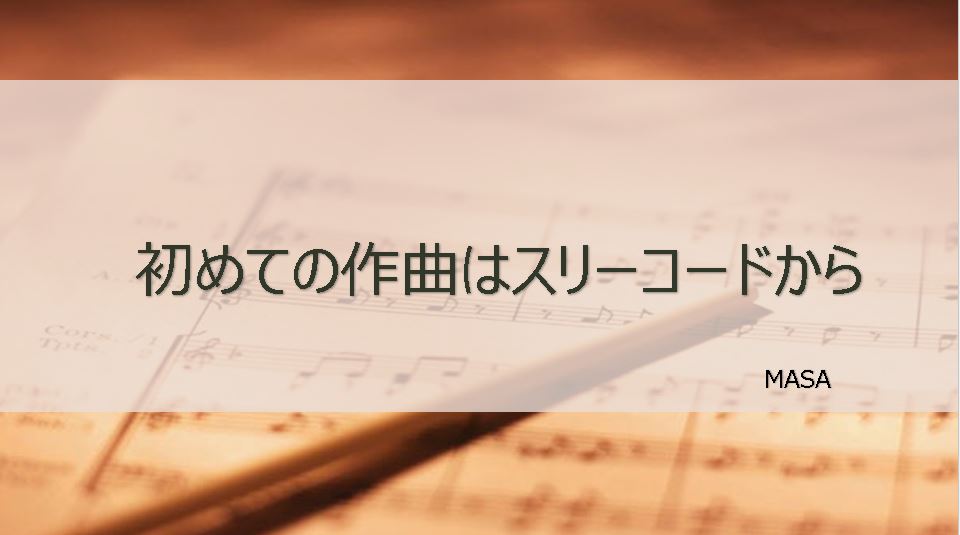


コメント